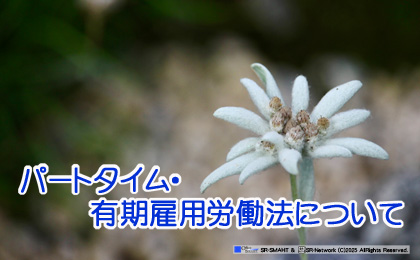 News Topics
News Topics パートタイム・有期雇用労働法について
「パートタイム労働者」は、正社員だけでなく、週の所定労働時間が短い「パートタイム労働者」や、契約期間が定められた「有期雇用労働者(契約社員・嘱託・アルバイト等)」も対象です。
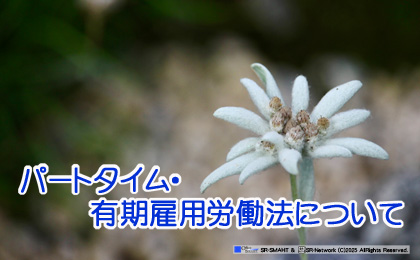 News Topics
News Topics  News Topics
News Topics  News Topics
News Topics 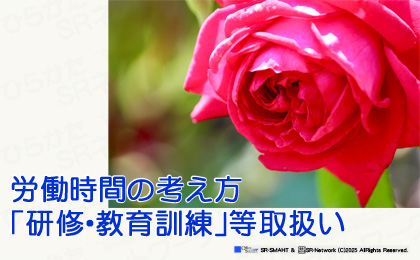 News Topics
News Topics 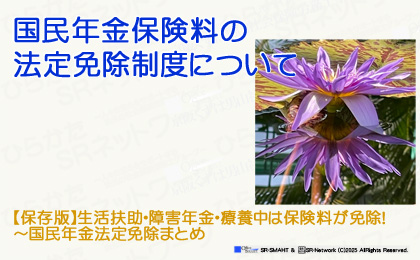 News Topics
News Topics 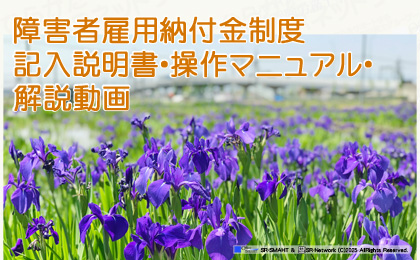 News Topics
News Topics 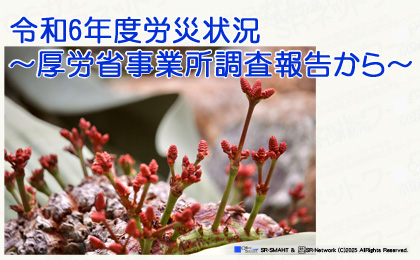 News Topics
News Topics  News Topics
News Topics  News Topics
News Topics 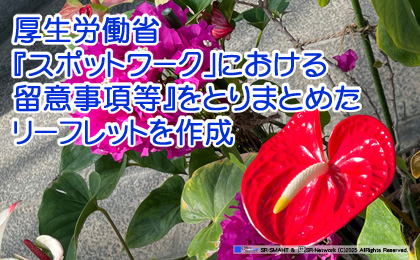 News Topics
News Topics 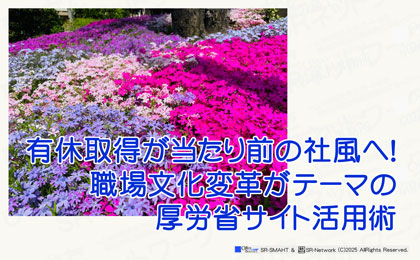 News Topics
News Topics  News Topics
News Topics 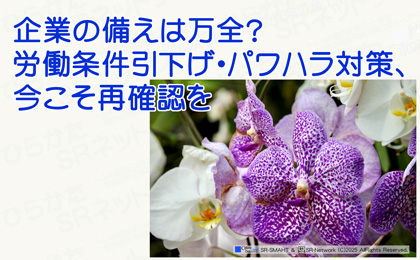 News Topics
News Topics 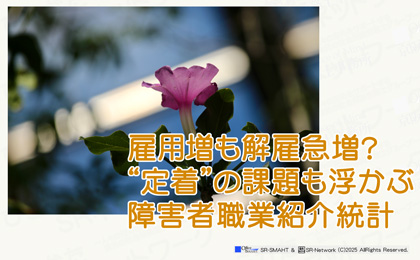 News Topics
News Topics 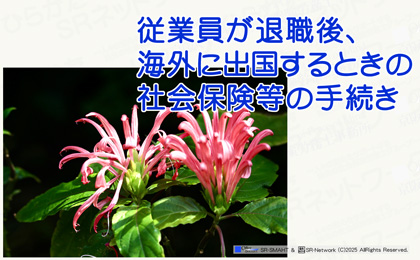 News Topics
News Topics  News Topics
News Topics  News Topics
News Topics  News Topics
News Topics 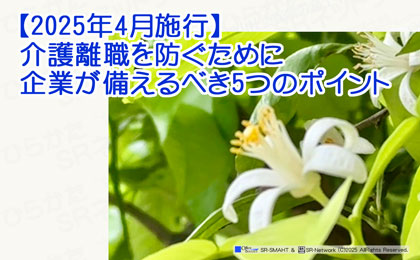 News Topics
News Topics 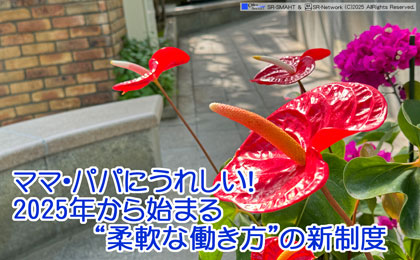 News Topics
News Topics 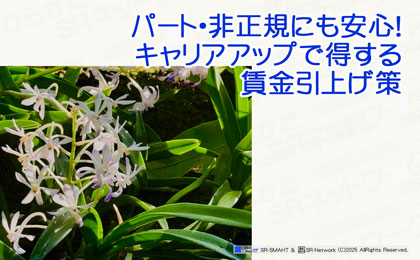 News Topics
News Topics  News Topics
News Topics  News Topics
News Topics 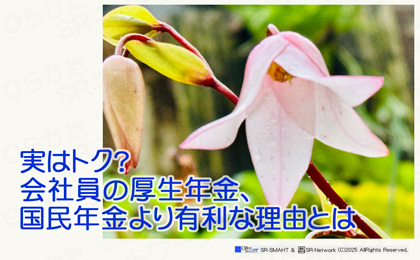 News Topics
News Topics 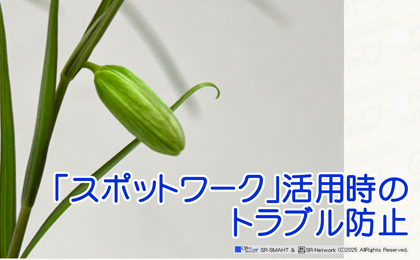 News Topics
News Topics 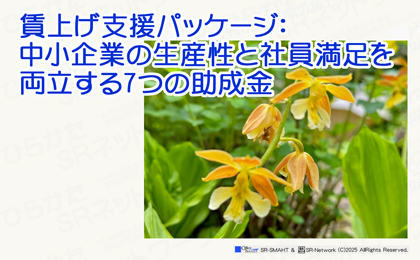 News Topics
News Topics  News Topics
News Topics 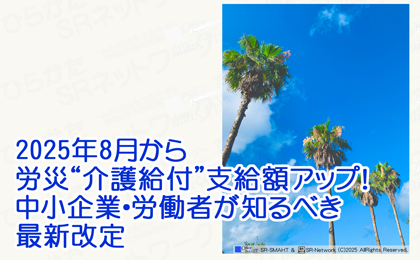 News Topics
News Topics 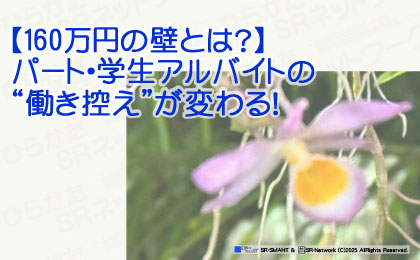 News Topics
News Topics 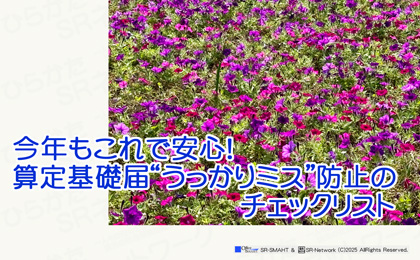 News Topics
News Topics